
井上 歩さん
Ayumi Inoue
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター所属 岐阜県出身。入社19年目。プレイングマネージャーとして営業とメイン講師を兼務し、研修の企画・実施・フォロー、外部講師の手配やサポートを担当している。国家資格キャリアコンサルタント、CDA資格(キャリア・ディベロップメント・アドバイザー)を保持。

武重 秀隆さん
Hidetaka Takeshige
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター所属 山口県出身。入社9年目。国家資格キャリアコンサルタント、全米・日本NLP協会認定 NLPプラクティショナー、LABプロファイル(R)プラクティショナー。大手広告代理店の営業、ゲーム会社の人事担当者を経て、2016年7月にキャリア入社。コーディネート部に勤務後、2020年4月より教育事業部へ。現在は営業業務を主体に、講師・サブ講師としても活躍中。
驚異的なリピート率を誇る、新入社員研修プログラム
『アソウの新入社員研修』には、さまざまな企業の新入社員が一堂に会して受講する「公開型研修(定員20名)」と、企業それぞれの重視ポイントを中心にプログラムをカスタマイズする「単独型研修」の2種類がある。また、内定者・入社時・フォローアップと、タイムリーにプログラムを提供。新入社員研修には毎年1700名を超える受講者が参加し、一度研修を導入した企業のリピート率は95%と非常に高い。
※教育研修の詳細ページはこちら

単独型研修でも、企業それぞれの事情によって研修で厚みを持たせる部分は変わる。例えば4月入社で12月まで長い実務研修を行う製造系企業の場合、実務研修が長いからこそ挨拶や報連相、メモの大切さなど、社会人としての基本行動を徹底的に教えている。また〝教えがいのある新人〟としてのマインドセットも重視する。

ゴルフ場のキャディー職の場合、第一印象やクラブの受け渡し方など、利用客から見て、頑張っている様子が伝わりやすい実践的な内容で構築します。接遇マニュアルをもとに「ここはこうした方が、もっと美しい動きに見えます」と提案する時もあります。
大きな反響を呼んでいるAHCの新サービス『キャリアビルド(新卒者対象、地域限定事務職)』の研修も、教育事業部が行っている。100%事務職なので、商取引の流れや帳票類(発注書、納品書、請求書など)を説明しながら、事務職の役割や目的を伝える。希望があれば、名刺の預かり方やお茶出しの仕方や心くばりも教える。事務職には、知っているのと知らないのでは大きな差が出やすいポイントが数多くあるからだ。


「入社後すぐ工場ラインに配属するので、名刺交換は教えなくていい」という企業もあります。その場合でもまったく教えなくて良いのか、将来、対外的な仕事が増える可能性を想定して少しは教えておいた方が良くないかと必ず確認します。
時間管理が重要だとか、担当範囲が幅広いのでタスク管理の意識を持たせたいとか、研修に厚みを持たせたいポイントは各社さまざま。そこを丁寧にすり合わせながらカスタマイズしていきます。
人事の前職経験が、提案に深みを増すケースも少なくない。例えば、武重さんにはゲーム会社の勤務経験がある。一般的にこの業界では、ビジネスマナーよりも発想力や開発力、技術力が優先される場合が多く、服装やコミュニケーションもラフな企業が多い。しかし武重さんは、「将来ポストが上がった時にそれで大丈夫ですか?」「マナーが身に付いていない部下や新入社員を十分にマネジメントできますか?」と必ず確認している。

私が「前職でゲーム会社の人事をやっていました」と話し出すと、新入社員の表情が変わり、興味深そうに耳を傾け始めます。実態に合わせて研修内容や講師を慎重に選定するのも、AHCならではですね。
アソウの新入社員研修では、業種業態、仕事内容、社風、社員層に関わらず、ビジネスマナーが基本である点を明確に伝えている。
他社との大きな違いは、丁寧なフィードバック
アソウの新入社員研修のリピート率が95%を維持している要因の一つに、内容だけではなく、丁寧にフィードバックをする点が挙げられる。実は、研修後のフィードバックを実施しない研修会社は少なくない。しかし、AHCでは研修後、報告書を提出するほか、参加者一人一人の所感や課題をフィードバックしている。このフィードバックがOJTにおける道しるべになるからだ。
公開型研修では人事担当者が同席しないので、参加者の様子はOJTを進める上で極めて大きなヒントになる。単独型研修では人事担当者がオブザーバー参加することもあるが、先方の感想をもとに課題を共有し、「一緒に育てていきましょう」というコンセンサスを得ながらフォローアップ研修につなげていく。

人事担当者と打合せをする武重さん。
公開型はどの企業にも通用する内容を、単独型は企業の要望に合わせてカスタマイズするが、プラスアルファの情報収集や、人事担当者の要望と実際の課題とのズレを確認する意味で、現場に足を運ぶ機会は多い。
例えば、住宅メーカーの接遇研修にあたって実際の現場を知るため、客のふりをしてモデルハウスへ覆面調査に行ったこともある。そこで得た情報に基づいた提案は深みが増す。求められたことを果たすため、自分たちが何をすれば良いのかを考え、そのために必要な行動はすべて行う。体感を通して課題を明確化し、ソリューションの構築を進めるのが、AHC教育事業部のスタンスだ。
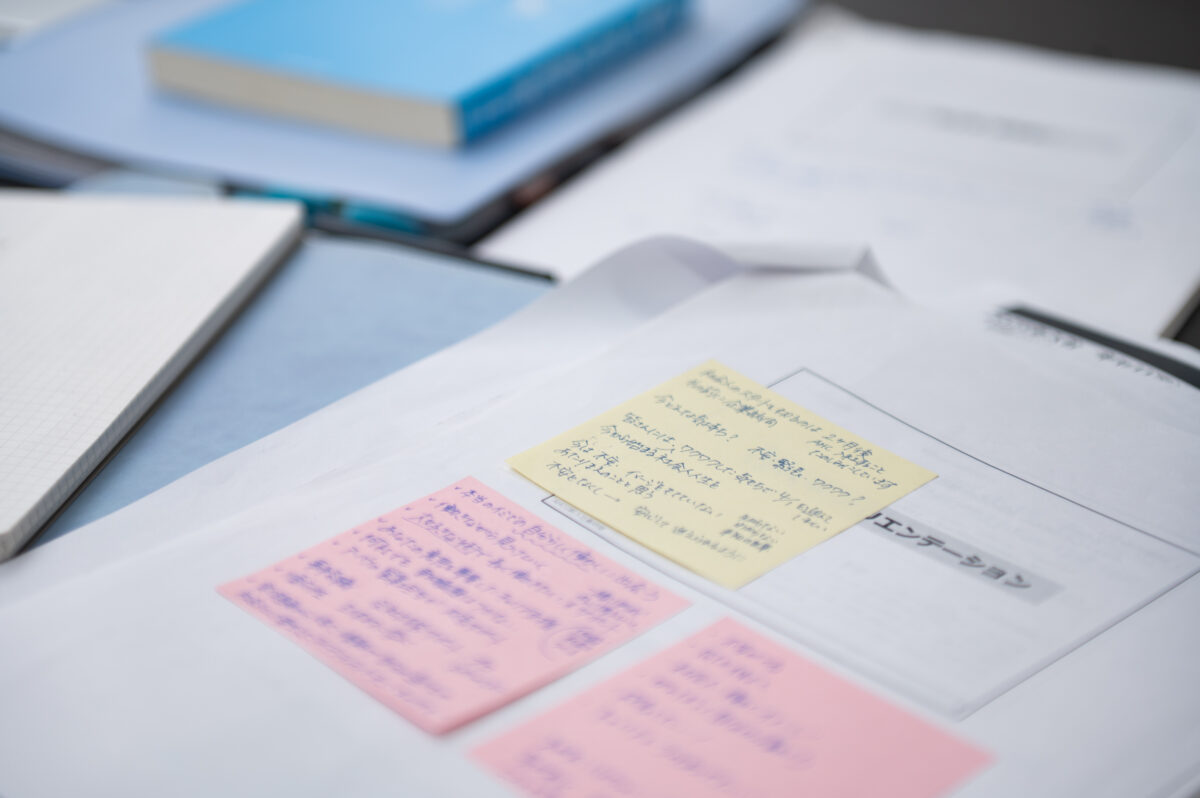
提案の際は、多くの資料を読み込んで準備を行っている。
若者の志向を理解し、自分の行動習慣を変える

打ち解けてくると「社会人になんてなりたくなかった」と、本音を吐露する新入社員も少なくありません。そこで私たちが「いや、実は仕事って楽しいんだよ」「むしろ社会人の方がチャンスは増える」と伝えることで、「思っていたより社会人っておもしろいかも」と感じてもらえるようにしています。
〝Z世代〟と呼ばれる彼らは、素直で協調性があり物怖じしない。考える癖が身に付き、思考力も優れている。人の意見を受容する共感力が高いのは、自分を受け入れて欲しい、認めて欲しいという承認欲求の裏返しだろうか。
一方で、思っていることを自分から発信しようとはせず、研修でも手が挙がらない。あてるときちんと答えるし、メールやチャットの返事はするが、行動や言葉には出てこない。アウトプット力が弱いので、良い意味の化学反応が起きにくい。
心の底にあるのは、「目立ちたくない、失敗したくない、だから挑戦しない」という深層心理。(やってみたい、やらないと)と思っていても、なかなか一歩が踏み出せない。

私は研修中、何度も「失敗はOK」と発信します。初日は順番にあてて様子を見て、2日目は「今のまま配属先に行っても大丈夫?」と投げかけ、自らアクションを起こしたくなる仕掛けをします。だから、自分から動けた時は大げさなくらいほめますね。

研修を行う井上さん。
ここ数年は、タイパ(タイムパフォーマンス)重視の若者が増えた。望んでいた配属先や仕事ではない場合に〝石の上にも三年〟は通用せず、「三年待つくらいなら、違う会社に行く」と早々に見切りをつける。ただでさえ新卒採用の難易度が高まる中、入社3年以内の離職率が4割弱という実態に、頭を抱える企業は多い。
とは言え、確かに時代とともに若者の考え方や感覚は変化するが、変わらない、変わってはいけない普遍的なものがある。学生は「ちゃんと働けるだろうか」と不安を抱いている。だから内定者・新入社員の段階で、働くイメージの解像度を上げていくことが重要なのだ。不安を取り除いて安心感を抱かせ、人生は成長する可能性が無限にあると教える。そして、自分で自分を成長させるマインドを育て、挑戦することの価値を伝えていく。

大切なのは「ほめる」ことです。今の管理職層は、ほめられ慣れてない世代。ほめる価値を実感できず、実践するのが苦手です。「挨拶の声が大きくて気持ち良いね」「期限前に報告してくれてありがとう」というレベルから始めれば良いのです。できた事実をほめる。承認されて嫌な若者はいません。ほめることをきっかけに、少しずつ関係性を構築してほしいですね。

彼らは、関係性が構築できている人から言われたことは受け入れますが、できていない人に何を言われても抵抗感を抱くだけです。本当に腹落ちしていないことは行動に移さない。理解はできても納得できなければダメなのです。納得できないのは関係性が弱いから。そして画一的な教え方も響きません。相手の表情を見ながら、一人ひとりに合わせた指導の仕方や伝え方が必要です。
腹落ちした若者の行動や変化は速い。それが顕著に表れるのが、入社半年後を目安に行うフォローアップ研修である。
4-5月の入社時は、何がわからないのかさえわからなかった。しかし半年後、フォローアップでふり返ってみると、ちゃんとできることが増えていると気づき、充実感と達成感を味わえた。自分が信じられるようになり、それが自信として積み重なっていく。アソウの新入社員研修は、新入社員の背中を押す研修なのだ。
本社で実施した、フォローアップ研修の様子。
研修に留まらない、多彩なソリューションを提供
今、多くの企業が若者の「離職(定着率)」に悩んでいる。彼らは、上司や先輩が疲弊している姿を見て「出世したくない」という志向も強い。
出世に興味がないから頑張りたくない。プライベートが充実する程度の給料で十分。残業もしたくない。最低限の仕事だけやっていたいから自己研鑽にも興味がない。そんな若者に対して、人事担当者の要望は「自己研鑽したくなるような、学びの魅力が伝わるような研修をして欲しい」というものだ。
そのためにAHC教育事業部では、「わかる から できる」を意識したプログラムを構築していく。腹落ちすれば素直に受け入れてくれるからこそ、「学んだことが実践に活かせた」「できなかったことができるようになった」「知らなかったことを学べてよかった」など、受講前と受講後の変化を体感できるプログラムを通じて、学びの魅力を伝えている。


私は、シーズアスリート(AHCGの障がい者スポーツ選手雇用センター)の浦田理恵さんが言われる、「行動や挑戦の先には、成功か成長しかない」という言葉をよく引用させてもらいます。「金メダルを獲ったアスリートの言葉だよ」と伝えると、「やってみようかな」と思うのか、手を挙げようとしなかった若者の表情が変わるのです。

「仕事は加点方式」という話をよくします。100点の持ち点が失敗して減るのではなく、みんな最初は0からのスタートで、挑戦すると加点が積み上がる。挑戦した結果が思い通りではなくても、そのプロセスから多くを学べるし、挑戦したことで引き出しが増える。だから安心して挑戦して欲しい、と伝えています。
最近は研修をきっかけに、さまざまな課題に対するソリューションを求められる機会が増えてきた。
人事評価制度を導入しようとしている企業に、他社の成功事例をChatGPTで収集して提供したり、人事評価に詳しいコンサルタントを紹介したり。また、あるインテリアメーカーでは、全国のショールームに勤務する派遣社員の研修を担当し、さらにカスハラ対策マニュアルの作成を依頼されている。他にも、「社内制度としてカウンセリングを導入したいので、社外カウンセラーの立場でカウンセリングをやって欲しい」という依頼もある。アソウの新入社員研修をきっかけに積み重ねてきた実績と信頼が、次のビジネスチャンスを生んでいる。

研修は事前準備が重要。研修に必要な情報を収集していく。

40年間培ってきた実績と信頼から、アソウ・ヒューマニーセンターグループ(AHCG)のポテンシャルが具現化できる機会が増えています。研修だけではない、派遣や紹介だけではない、「そんなことまでやってもらえるの?」というお客さまの感動を、私たちがどれだけ生み出せるか。それがグループ社員全員に共通する、次のテーマだと思っています。
私も研修講師として、1人の社会人として、常に新しい知見を積み重ねながら成長できることに心が躍ります。そうやってインプットしながら、研修や営業現場でアウトプットしていく。私たちの生きる姿勢が若者の心を動かす。私はそう信じています。
















公開型研修も内容は毎年変えます。社会背景、新卒者の特徴や課題が年ごとに変わるからです。前年に参加した企業の感想や、登壇した講師の意見を参考にしながら、内容や進め方を決めていきます。毎年アップデートする感じでしょうか。