
長田 晋平さん
Shinpei Nagata
株式会社 福利厚生倶楽部九州 南九州営業本部 熊本オフィス 所長代理 福利厚生管理士。鹿児島県出身。現在は株式会社福利厚生倶楽部九州のリーダーとして、南九州エリア(熊本・宮崎・鹿児島)を担当。後輩からは「仕事ができ、相談すると最適解をくれる頼もしい先輩」「クールな一方で、しっかり叱ってくれる」「理論的な説明がとてもわかりやすい」と、絶大な信頼を寄せられている。

赤松 宏明さん
Hiroaki Akamatsu
株式会社 福利厚生倶楽部九州 本社営業部 副主任。大分県出身。大学卒業と同時に株式会社アソウ・ヒューマニーセンターへ入社して人材ビジネスに従事。その後、株式会社福利厚生倶楽部九州へ転籍。新卒入社6年目。現在は、福岡県内と、大学時代を過ごした長崎県内を担当。新入社員時のメンターは長田さん。人物評は「素直で明るい」「誠実、実直、仕事への情熱に満ちている」「意見が言いやすい雰囲気を作ってくれる先輩」と、ムードメーカーとしての信頼が厚い。

清水 尚武さん
Hisatake Shimizu
株式会社 福利厚生倶楽部九州 本社営業部 所属。福岡県出身。大学卒業後、家電量販店で接客業務経験を積む。2023年11月、株式会社福利厚生倶楽部九州へ転職し、現在2年目。担当は福岡県内で、入社時のメンターは赤松さん。先輩からは「しっかりとした丁寧な仕事ぶり」「雑務も快く引き受けてくれる」「期待の星」「素直で、頭がいい」「わからないことは何でも質問して解決する基礎が身についている」という評価を受けている。
九州における、抜群の知名度とシェア
ライフスタイルや価値観の多様化で、個人の悩みやニーズは多岐にわたる。しかし、それをカバーするだけの福利厚生制度を、自社で充実させるのは難しい。また、全企業の99.7%を占める中小企業に(※)大手企業と同等の福利厚生を制度整備するのも限界がある。
だが、福利厚生をアウトソーシングすることで、中小企業にも充実した制度構築が可能になるという認識が、近年着実に進んでいる。
※出典 総務省「平成26年経済センサス-基礎調査」
総務省・経済産業省「平成28年、令和3年経済センサス-活動調査」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213chukigyocnt.html
九州の福利厚生アウトソーシング業界では7割を超える圧倒的なシェアを持ち、中小企業をはじめ医療機関、学校法人、自治体など、業種・業態を問わず多数の会員企業から支持を得ている。
これは、導入団体数において業界トップの〝リロクラブ〟への高い認知度と、同社独自の、地域に根差した魅力あるサービスメニュー開発によるところが大きい。


2017年に沖縄、2019年は熊本に拠点を開設できたのも、地元の企業や団体、提携先の皆さまとの接点が着実に増えた証です。アソウ・ヒューマニーセンターグループ全体の信頼と連携を通じて、「地元で使える福利厚生サービス」「身近な人事・労務の相談役」という認識が広がっていると感じます。
同社では、定期的にサービス拡充に向けたアンケートを実施し、要望の多い施設との提携を順次拡大している。また、利用促進ツールとして、九州北部・九州南部・沖縄それぞれのエリア会員誌『FUN』を、年6回、偶数月に発行している。
機能面も随時改善を進めており、直近では15の宿泊サイトを横断検索できるようになった。サービス検索アプリの改善や、マップ検索機能の使い勝手が良くなるなど、利便性は確実に上がっている。サイトのビジュアルも印象の良いレイアウトへと進化した。

2025年4月に改修した、サービス検索アプリ。マップ検索機能ではマップ上で利用できる店舗が表示されるため、お客様からもご好評をいただいている。
※福利厚生倶楽部 サービスページはこちら
入社前から利用できるサービスで、内定辞退を防止
ここ数年、特に注目されているサービスが「内定者福利厚生倶楽部」である。内定者は、最短で入社前年の8月から既存従業員とほぼ同等の福利厚生メニューを利用できる。また「Eフレッシャーズ」という機能があり、eラーニングやSNS(チャット)機能を通じて、内定者フォローがしやすいというメリットがある。内定者福利厚生サービスを通じて、会員企業の内定者数千名にも毎年サービスを提供している。

お客様への提案にあたって、社内での連携は欠かせない。それぞれの事例や情報等を共有しながら、より良い提案へ落とし込んでいく。

内定辞退の防止は、採用担当者にとって大きな課題です。新卒者の多くは社会に出ることへの不安を抱えており、何らかのフォローが必要。とは言え、採用担当者が限られた時間とマンパワーできめ細かにフォローするのは負担が大きい。
でも、SNS(チャット)機能を活用すれば、内定者の不安を取り除く機会が増えます。自己成長を促しながらサポートできるし、採用担当者の業務負担は軽減します。そのため、「内定者福利厚生俱楽部」をきっかけに新規契約する団体・企業が増えている状況です。

「内定者福利厚生俱楽部」のSNS機能は、内定者と採用担当者が気軽にコミュニケーションを取れます。一般的なSNSと違ってその企業と内定者限定のチャットなので、個人情報など情報の秘匿性が高く、学生も安心して利用できるようです。

以前から、新生活に必要なスーツや家電の購入割引、引越費用割引などの利用者は多かったですね。最近は、社会人としての基礎やビジネスマナー、Microsoft Officeアプリケーション(Word、Excel、PowerPoint)の基礎が学べる、eラーニングも人気です。
学生にとって福利厚生制度の充実度は、就職先を選ぶ上で重要な基準になっている。企業にとっては、ブランディングを大きく左右する要因であり、内定辞退の防止を含めて優秀な人材確保の有効な手段となっている。

お客様と電話をする赤松さん。お客様の声にしっかりと耳を傾けて、信頼関係を築いている。
「健康経営」の広がりと、多世代ニーズに応えるメニュー
同社のサービスが、従業員の生活支援やエンゲージメント向上に活用されていると実感する機会は着実に広がりつつある。「健康経営」への関心の高まりとともに、スポーツクラブや人間ドック補助サービスの利用が増えているのも、その一例だろう。現在、全国的に、健康経営を実践している優良企業を表彰する「健康経営優良法人」の認定取得への関心が高まっている。九州・沖縄地区でも、認定取得に向けて健康経営に取り組む中小企業が増え、人的資本への投資を強化する傾向が強まってきた。

従業員の健康維持や増進を経営課題と捉え、健康管理を経営的な視点で戦略的に実践するのが「健康経営」です。従業員の健康に関する投資は、生産性向上と人材定着に有効ですし、企業価値を高めることにつながります。

お客様と商談を行う長田さん。現場のリアルな声に寄り添いながら、最適なソリューションの提供につなげている。
また、育児介護休業法の改正(2025年4月1日施行)を機に、育児支援や介護支援メニューの充実化も進み、一時保育利用や介護保険限度額オーバー分の補助など、リアルな困り事を支援する実践的サービスの利用者も増えている。
従来の余暇支援に加えて、最近は特に、独身者から子育て世代、介護世代といった多世代ニーズに応える、生活支援メニューの充実がめざましい。
福利厚生は〝時代を映す鏡〟であり、課題解決の有効手段
「福利厚生」に対する関心が高まった背景には、内定者の辞退防止、「健康経営」の推進、総合的な企業ブランディング、多世代ニーズに対するリアルな生活サポートなど、さまざまな要因がある。最近では、物価上昇もその一つと言えるだろう。

昨今の物価上昇をカバーするほどの昇給を、すべての企業が対応するのは現実的ではありません。その代わりに〝実質的な可処分所得を増やす〟という目的で、福利厚生アウトソーシングサービスの導入を検討する中小企業が、増えているようです。

福利厚生は〝時代を映す鏡〟です。社会のニーズに沿って、次々にサービスメニューが広がっている。だからこそ、福利厚生サービスの積極活用は、組織における課題解決のきっかけになり得ます。そこから組織が抱える課題が見えてくるし、解決に向けたヒントも得られます。福利厚生は、社内改革への一歩と言っても過言ではありません。

真剣ながらも、和やかな雰囲気で打合せを行う赤松さんと清水さん。先輩社員とのフランクなやりとりが、若手社員の挑戦を後押ししている。
同社にとって、今後に向けた課題は「サービスの周知」である。利用が活性化することで、社員の満足度が上がり、組織の課題解決の一歩となる。これからもコツコツと、会報誌の発行や事例紹介など既存の手法を通じて、利用促進を徹底していく。
また、「健康サポートアプリ」や「人的資本エンゲージメントサーベイ(ストレスチェック)※」など、人事・総務部門の解決ツールとして提案できるメニューも充実している。そこからアソウ・ヒューマニーセンターグループが有する知見につなげ、部門を超えた連携で顧客の課題解決に貢献することへの期待が高まっている。
※「心身の健康状態」と「エンゲージメント」を可視化する組織診断ツール。

福利厚生をきっかけに社内課題が浮き彫りになる。あるいは人的課題を抱えた企業の解決プロセスで、福利厚生がクローズアップされる。そんなケースがますます増えるでしょう。これまでも、「新卒採用がうまくいかない」「媒体を使っても効果を実感できない」「教育面で課題を抱えている」「優秀な中核人材をU・Iターンで採用したい」など、さまざまなきっかけから、グループシナジーを生かして解決に至ったケースがありました。
同社の福利厚生サービスは、加入企業・団体の業務負担を軽減し、従業員とその家族の生活や健康をサポートし、サービス利用を通じて地域社会を活性化する。まさしく〝三方良し〟の事業であり、個人と地域経済を橋渡しする役割を担っている。
企業・団体の困り事を解決する手段として活用される時代を迎えた福利厚生が、今後、組織や社会にどのような変革や進化をもたらすのか、大いに期待したい。


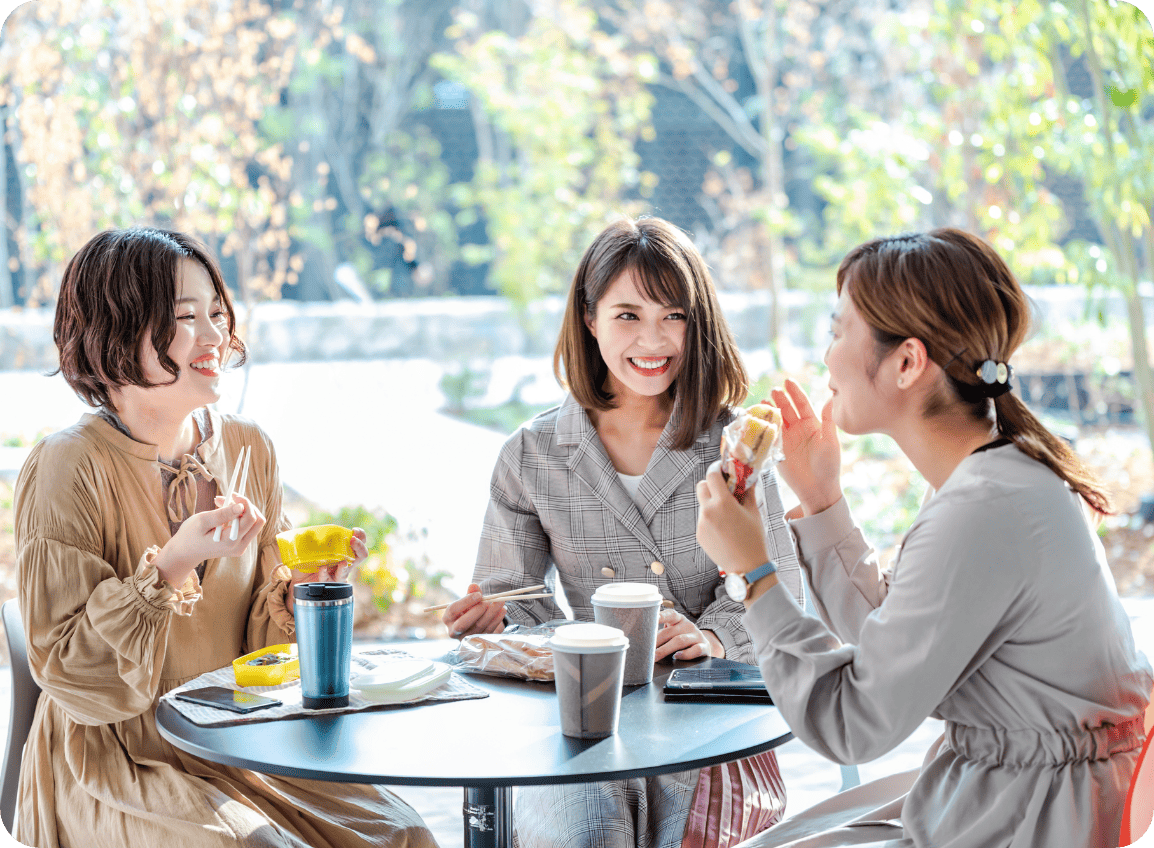










一貫して取り組んできたのは、徹底した「地域のサービスメニュー開拓」です。以前のアウトソーシングは、サービスメニューの多くが関東圏や関西圏中心でした。そこで、九州の方々が地元の施設を気軽にご利用いただけるように、利用サポート部門とサービス開発部門を社内に設け、両輪でサービス向上と市場開拓を進めてきました。